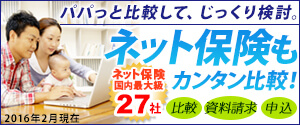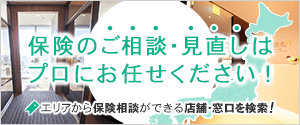がんで働けなくなった場合の備えを考えよう その2

がんへの備えは、高額になると思われる治療費などの支出だけでなく、これまで通りの収入が得られなくなった場合の備えも必要です。
既にリタイアし、年金収入で生計を立てられている方であれば、がんになって生活が一変したとしても年金収入に変わりはありません。
しかし、現役で働き、その収入で生活を支えている方ががんになってしまった場合には、これまでのようには働けなくなるリスク、それにより収入が減ってしまうリスクが大いに考えられます(参考コラムがんで働けなくなった場合の備えを考えよう その1)。
働けなくなり収入が減った場合のリスクに保険で備えるならば、どのような保険が活用できるのかをみていきましょう。
がんで働けなくなり収入が減るリスクに活用できる保険商品例
①がん収入保障保険
がんと確定診断された場合、一定期間もしくは存命中は年金が支払われます。がんと診断された時の収入減少のリスクに焦点をあてたがん保険です。
診断された時点で支払要件が満たされるため、従前と変わらずに仕事を続けていても支払われます。
②がん保険のがん診断給付金
がんと診断された時点で一時金が支払われる給付金で、最近のがん保険の基本保障になりつつあります。
一括で支払われたお金を治療のためだけでなく、生活を守るための収入の補てんにすることもできます。
③生前給付保険
がんだけでなく、三大疾病や特定疾病など契約の所定の状態と診断された際に、一括で保険金が支払われる保険です。
一括で支払われたお金を、治療のためだけでなく生活を守るための収入の補てんにすることもできます。
④就業不能保険/所得補償保険(特約)
がんに限らず、病気やケガによって働けない状態になった場合に、毎月、給与のように給付金が支払われます。
働けない状態になって一定期間が経過してから、補償が開始されます。
保険商品を選ぶポイント
上記のように、がんになって働けなくなった際の収入が減るリスクに備えられる保険には、それぞれの特徴があります。
自分にはどのような保険が適切であるのかについて考える上で大切なことは、どのタイミングでどれだけの保障(補償)が見込める保険なのか、ということです。
もし、がんになって働けなくなった場合を想定し、その時にでも得られる収入と生活をする上で必要な支出の両面から考えましょう。
この場合、がん治療にかかるお金は別として、普段の生活を送るために必要な支出を収入で補えない部分を保険でまかなうことも検討しましょう。
まず、支出についてですが、日々の生活にかかるお金や子どもの教育にかかるお金など、がんになっても変わらずに必要となるものがほとんどでしょう。
ただ、三大疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞)になった際には、住宅ローンの支払いが免除される保険に加入している場合の住宅ローン返済分だけは、支出から省いて考えることができます。
収入は、会社員か自営業か、会社員であっても雇用の形態や結んでいる雇用契約内容によって、大きく違ってきます。
なぜなら、仕事が続けられなくなった時の収入源となる公的制度や勤務先の制度を受けられるかどうかの違いによるからです。
正規雇用の会社員の方であれば、有給休暇や傷病手当金により、会社を休んでいても一定期間は給与や手当金が支払われます。
勤務先によっては、私傷病休職制度や傷病手当金の付加給付制度もあります。つまり、がんと診断され、治療や体調不良で仕事ができなかったとしても、最低で1年6カ月間は収入が途絶えてしまうことはないということです。
ただ、期間が限られており、働いている時ほどの収入にはならないため、補てんという形で保険を考えるといいのではないでしょうか。
一方で、自営業の方には、有給休暇も傷病手当金もありません。
がんかどうかの検査を受けるために仕事を休まなければならない場合も出てくるでしょうから、がんと診断される前から収入が減少してしまう方もいらっしゃるでしょうし、働けないことがすぐに無収入に繋がってしまう方もいらっしゃるでしょう。
がんと診断されたタイミングで保険金を受け取れる保険は、がん治療だけでなく生活費としても使えるので、備えの一つとして準備しておくと安心だと思われます。
がんになっても働きつづけられる社会への期待とともに
がんになって働けなくなった時に、収入の一部をまかなうことができる保険は、非常に心強い存在です。
しかし本当は、がん患者さんが保険に頼りすぎることなく、自分らしい生活の中で働き続けられたら、生きがいにもなるのではないでしょうか。
がんになっても退職を余儀なくされることなく、治療中であっても働くことを受け入れてくれる社会であってほしいと私は願います。
がんと付き合いながら働ける社会になっていくことに期待をしながら、がんになって働けなくなった場合には、「がんになった時点で半年分の生活費として200万円」など、どのタイミングでどのくらいの保障が自分には必要なのかを考えて、保険選びをしましょう。

-
コラム執筆者プロフィール
川崎 由華 (カワサキ ユカ) マイアドバイザー.jp®登録 - CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、平成24年度日本FP協会「くらしとお金の相談室」相談員。
前職ではがん領域の薬を扱う製薬会社に勤務。
現在は2児の母をしながら、主婦向けのマネー講座や個人相談、執筆等ファイナンシャルプランナーとして活動中。
お金の数字だけの問題でなく、気持ちも汲み取れる身近で気さくな存在のファイナンシャルプランナーをモットーにしている。

-
コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー 川崎 由華
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
掲載日:2020年3月31日
がんで働けなくなったときに頼れる公的制度
万一がんと診断されたときのことを考えて、がん保険の加入を検討されている方はいらっしゃるかと思いますが、がん保険に加入する前に、私たちが受けられる公的制度について把握しておきましょう。

表1 医療費が高額になった場合に受けられる公的制度
| 名称 | 概要 | 対象 |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、1カ月(月の初め~終わり)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を受け取れる制度。 | 公的医療保険が適用される診療に対し、患者が支払った医療費。 |
| 医療費控除 | その年の1月~12月までに支払った医療費が一定の金額を超えるときは、その医療費の金額をもとに計算される金額の所得控除を受けられる制度。 | 自己または自己と生計を共にする配偶者や、その他の親族のために支払った医療費。 |
資料:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」、国税庁ホームページをもとに作成
表2 働けないことで生活に不安がある場合に受けられる公的制度
| 名称 | 概要 | 対象 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 会社員や公務員など、健康保険や共済などに加入されている被保険者本人が、病気やケガで働けなくなり、収入が減ってしまった場合に、生活の保障を受けられる制度。 | 病気やケガで連続する3日間を含み4日間以上仕事を休み、給料や障害・老齢年金などが支払われていない場合(療養中の給料が傷病手当金より少ないときは、差額が支給される)。 |
| 障害年金 | 病気やケガなどが原因で、一定程度の障害が継続する場合に、生活の保障を受けられる制度。 | 病気やケガによって医療機関に初めて受診した際、加入していた年金によって受給できる障害年金が異なる。等級は1級が一番重度で、3級が一番軽度となり、障害の状態が重いほど受給できる年金額も多くなる。 |
資料:国立がん研究センターがん情報サービスホームページ、厚生労働省ホームページをもとに作成
表3 自身や家族の介護が必要となった場合に受けられる公的制度
| 名称 | 概要 | 対象 |
|---|---|---|
| 介護保険制度 | 介護保険への加入は40歳以上とし、被保険者となる40歳以上の方が病気や加齢で要介護状態になった場合などに、介護サービスを受けられる制度。 | 65歳以上の方は原因を問わず要介護認定などと認められた場合、また40~64歳の方は、加齢による特定疾病(末期がんなど)が原因の場合。 |
| 介護休業給付制度(雇用保険) | 雇用保険の被保険者の方が、要介護状態にある家族を介護するために介護休業をした場合に、一定の要件を満たすと介護休業給付を受けられる制度。 | 雇用保険の被保険者が、介護休業開始日前2年間に、「日給者は各月の出勤日数」「月給者は各月の暦日数」が、11日以上ある完全月が12カ月以上ある方。 |
資料:厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」、厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します 令和元年度版」をもとに作成
検討される際、条件や手続き方法などの詳細は各機関のホームページなどで確認することが可能ですが、分かりづらい場合は直接問い合わせて確認すると良いでしょう。
今すぐ相談したい方はこちら
![]()