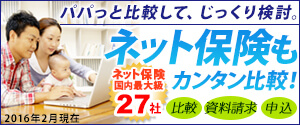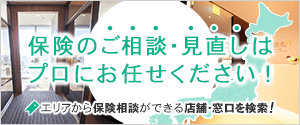がん治療にかかる費用を知ろう

がんは(一部のがんを除き)、早期発見することで早期治療・早期完治に繋げることが出来る病です。
しかし、症状が出にくいがんの場合、定期的な検査を受けていなければ、がんと気付くことが遅くなってしまいます。
がんは、じわじわと周辺の組織に浸潤するうえ、血液やリンパ液の流れにのって全身へと広がっていく性質があり、そうなると切除手術だけでは済まず、抗がん剤を使っての治療や放射線での治療、最近では医療の進歩で免疫細胞療法など選択肢も増え、がんの進行度や性格によって、治療法や薬を変えていかなければなりません。
一体、どのくらいのお金がかかるのだろう?
どういう治療をして、どういう薬を使ったら、どのくらい自費で負担しないといけないのだろう?
気になりますよね。
参考に具体例から考えていきましょう。
血便の症状から受診したところ、結腸がんが見つかりました。
結腸がんの切除手術をし、再発予防として外来で抗がん剤治療を6ヶ月間受けました。
この場合の治療費総額は、概算で約198万円。
高額療養費制度を利用し、自己負担総額は約37万円(一般所得者)となります(がん治療.com参照)。
しこりを感じて検査をしたところ、乳がんが見つかりました。
早期発見とはいかず、手術でがんを切除した後、再発予防として分子標的治療薬とその他抗がん剤を使った治療、そして放射線治療、ホルモン療法を行うことになり、5年を要しました。
全て保険適用の治療でした。
この場合の治療費総額は、概算で約660万円。
高額療養費制度を利用し、自己負担総額は約123万円(一般所得者)となります(がん治療費.com参照)。
いかがでしょう?
基本的には高額療養費制度を利用して、ある程度の余裕貯金があれば、がんの治療費も恐れることではないと思います。
しかし、保険適応外の治療を選択するべきケースもあるでしょう。
また「切除」だけで済まないならば、長期的な治療が必要になったり、保険適応の薬しか選択しなくても、薬によっては1本何万円、1粒何千円という高価なものもあり、高額な自己負担額になるケースもあります。
長期的ながん治療によって、これまでの就業ができなくなってしまうことだって考えられます。
そこで、経済的支援をしてくれるのが「がん保険」でしょう。
とはいえ、がん保険の加入の前に早期発見のための定期的な健康診断を欠かさないことが、体にもお金にもなにより安心材料になることをお忘れなく!

-
コラム執筆者プロフィール
川崎 由華 (カワサキ ユカ) マイアドバイザー.jp®登録 - CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、平成24年度日本FP協会「くらしとお金の相談室」相談員。
前職ではがん領域の薬を扱う製薬会社に勤務。
現在は2児の母をしながら、主婦向けのマネー講座や個人相談、執筆等ファイナンシャルプランナーとして活動中。
お金の数字だけの問題でなく、気持ちも汲み取れる身近で気さくな存在のファイナンシャルプランナーをモットーにしている。

-
コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー 川崎 由華
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
掲載日:2020年4月24日
がん治療の費用は、どんな保障で備える?

がん保険にはさまざまな保障の選択肢があるため、どのような保障を選べば良いのだろうと悩み、迷うことも少なくないと思います。
実際にがんと診断されたときのために、どのような保障を選択しておけば安心できるのでしょうか。
がん保険の保障のひとつとして、がんと診断されたときに給付金が受け取れる「がん診断給付金」を主契約で備えている商品が多くあります。
このがん診断給付金は、保険期間を通じて1回受け取れる商品と、複数回受け取れる商品があります。
また、先進医療を選択・受診したときの治療費に備えられる「がん先進医療保障」や、入院時に日々かかってくる費用を補える「がん入院給付金」、治療のために通院したときの費用を補える「通院給付金」などの保障もあります。
このような保障で備えることで、高額療養費制度を含めた公的医療保険ではカバーしきれない、自己負担部分の費用を補うことができます。
がんは再発する可能性もある病気なので、がん保険の保障は、複数回受け取ることのできるがん診断給付金や、がん入院給付金、先進医療保障などをベースに、現在がんの治療において主流になりつつある通院の保障も検討するのが良い方法のひとつでしょう。
今すぐ相談したい方はこちら
![]()