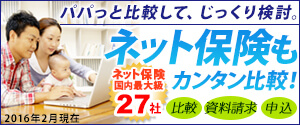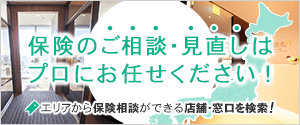ひとり暮らしの場合、入るべき保険は?

ひとり暮らしの場合は、医療保障を優先的に準備して!
ひとり暮らしの方が最優先で準備すべきなのは、自分が病気・ケガで入院した際の医療費負担や収入減に備える医療保障です。
医療保障の準備の仕方には、2通りあります。
死亡保障の保険を主契約にし、特約で医療保障をつける方法と、医療保障を主契約にした医療保険に入る方法です。
扶養家族がいないひとり暮らしの方には、遺族の生活保障のための死亡保障は必要ない場合が多いので、医療保険を優先して考えるといいでしょう。
では、どのような医療保険を選べばいいのでしょうか。選び方のポイントは、以下の通りです。
●保障期間のタイプを選ぶ
医療保険には、一定期間(10年が多い)ごとに一定年齢(80歳など)までの保障を更新していく更新型と、加入時から死亡するまで保障が続く終身型があります。
更新型は更新ごとにそのときの年齢と保険料率で保険料が再計算されますので、保険料は徐々にアップしていきますが、更新のタイミングで保障の見直しができます。
それに対して、終身型は途中で保障が切れることはなく、保険料も一定ですが、保障内容も変更がありません。
●入院日額と保障内容を選ぶ
生命保険文化センターの調査結果を見ると、入院1日当たりの自己負担額の平均は16,000円程なので、入院日額は1万円~2万円を目安に準備しておくといいでしょう。
ただし、保険料が高いと考えられる方は少額でもいいので準備しておくことが大切です。
保障内容は、入院・手術・先進医療の3つがあればひとまずは安心です。入院については、1入院の保障限度日数は60日型が主流です。
手術の保障は、手術の種類に関係なく定額の商品と、手術の種類によって入院給付金日額の10・20・40倍の倍率の商品があります。
その他の選択ポイントは、保障する手術の種類が少ない商品(約500~600種類)と多い商品(約1,000種類)があり、これは、多いに越したことはありません。
先進医療については、通算限度額は1,000万円が一般的ですが、2,000万円の商品も登場しています。
- 医療保険選びの豆知識
- 終身型医療保険の保険料の払い方は3タイプある
- 終身型の保険料の払い方は、「1.死亡するまで払う終身払」「2.死亡するまで払うが高齢期(60歳・65歳など)は半額になるタイプ」「3.60歳・65歳などで保険料が払い終わる有期払い」の3タイプ。同じ保障内容なら、毎月の保険料は1⇒2⇒3の順に高くなります。高齢期に保険料を負担するのは不安でしょうから有期払いを選ぶのが無難。でも、保険料が高く感じるなら1か2の方法を考えましょう。
ファイナンシャルプランナー 小川 千尋
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
こちらの記事も読まれています
掲載日:2019年10月16日
一人暮らしにもすすめたい就業不能保険・所得補償保険
一人暮らしの方が医療保険に加入する際には、傷病により働くことができない期間ができることによって、一定期間収入が途絶えてしまうリスクがあることを考慮しましょう。
被雇用者が傷病を原因として就業ができない場合には、会社の健康保険組合や全国健康保険協会から「傷病手当金」が支給されます。
ただし、国民健康保険の対象者である自営業者やフリーランスの場合、傷病手当金は任意給付となっています。
現在、実施している市町村はありませんが、国民健康保険組合では支給される場合があるため、自治体や組合への確認をしておきましょう。
傷病手当金の給付が行われない場合、傷病により働けない期間の生活費を考える必要があります。
いざという時に不足した収入分をカバーする手段として、傷病手当金の他に生命保険会社が販売する「就業不能保険」や損害保険会社が販売する「所得補償保険」があります。
自営業者やフリーランスで一人暮らしの方はリスクに備えるために、就業不能保険や所得補償保険への加入を検討されても良いかもしれません。
こちらの記事も読まれています
今すぐ相談したい方はこちら
![]()