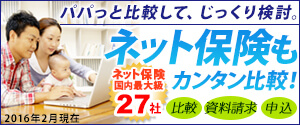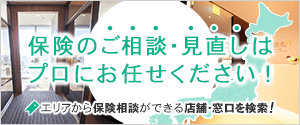ライフステージごとの自動車保険のポイント

一般社団法人日本自動車工業会の「乗用車市場動向調査2011年」によると最近は女性の自動車ユーザーが増えてきているようです。
カーライフは子育て期、子どもの独立期等のライフステージによって変わります。どのように車を利用するかによって、自動車保険の契約方法にもポイントがあります。
【ケース1】
まだ子育て中。夫婦2人で、車1台を乗る場合
●記名被保険者を誰にするか?
自動車保険を契約するときには「契約者」と「記名被保険者」を決めます。「契約者」とは、自動車保険を締結し、保険料の支払いをする人のことです。「記名被保険者」とは主にその車を使用する人です。どちらも自動車の所有者でなくても構いません。
女性は、買い物や用足し等生活手段の一部として自動車を使うことが多く、自動車保険を契約するのは夫、主に運転するのは妻、という場合もあります。この場合、「契約者」と「記名被保険者」は異なります。「記名被保険者」は特約の補償範囲や運転者の範囲を決める基準となります。例えば「ゴールド免許割引」は「記名被保険者がゴールド免許である」ということで割引になります。夫婦で車を使用している場合は、誰を「記名被保険者」にするかによって保険料や補償の範囲が変わってきます。
●補償の範囲
自動車保険では「記名被保険者」は1人ですが、補償の範囲は1人ではありません。記名被保険者を中心として、記名被保険者と関係のある一定の範囲の人(配偶者、同居の親族、別居で婚姻歴のない子)、記名被保険者から許可を得て車を使用する人が補償の範囲となります。この補償の範囲を限定すると保険料が安くなります。
| 限定の種類 | 補償される人 | 割引率 |
|---|---|---|
| 家族限定 | 記名被保険者、配偶者、家族(同居の親族、別居で婚姻歴のない子)のみ | 低い 高い |
| 夫婦限定 | 記名被保険者、配偶者のみ | |
| 本人限定 | 記名被保険者のみ |
自動車を運転するのが夫と妻だけなら、夫婦限定にしておきましょう。今まで夫のみが運転者で「本人限定」になっていた車に妻も免許をとって運転する予定なら、免許を取得してから「夫婦限定」に変更できます。
| 年齢条件の種類 | 補償される人 | 割引率 |
|---|---|---|
| 21歳未満不担保 | 21歳以上の人 | 低い 高い |
| 26歳未満不担保 | 26歳以上の人 | |
| 30歳未満不担保 | 30歳以上の人 | |
| 35歳未満不担保 | 35歳以上の人 |
年齢条件は保険会社ごとに年齢区分が異なります。この年齢条件は、その車を運転する記名被保険者、配偶者、同居している親族の中で最も若い人に合わせます。誕生日を迎えたら年齢条件の設定の見直しをしましょう。
【ケース2】
子どもが車に乗り始める場合
●子ども特約
現在の自動車保険が「夫婦限定」「35歳未満不担保」の契約で、21歳の同居の子が親の車を運転することになったら・・・。この場合、まず「夫婦限定」を「家族限定」に変更しましょう。次に年齢条件ですが、子の年齢に合わせると「21歳未満不担保」になり、保険料が高くなります。そこで「子ども特約」を付ける方法があります。保険会社によっては、「子ども追加特約」「子ども運転者年齢限定特約」「子ども年齢限定特約」等と呼ばれています。「子ども特約」は、記名被保険者の子について、主契約とは別に年齢条件が設定できる特約です。年齢条件が「35歳未満不担保」となっている保険に、「21歳未満不担保の子ども特約」を付ければ、35歳以上の親も21歳以上の子も補償されます。契約を「21歳未満不担保」に変更するよりも保険料が安くなります。
ところで1人暮らしで大学に通う子がたまに実家に帰り、親の車を運転する場合はどうでしょう。現在の自動車保険が「35歳未満不担保」「夫婦限定」の契約の場合は、「夫婦限定」を「家族限定」に変更します。この場合、年齢条件を変更する必要はありません。別居している子は運転者の年齢条件の限定は適用外だからです。
【ケース3】
同居の子が車を新しく購入し、保険契約をする場合
●セカンドカー割引
自動車の保険料は等級によって割引率が変わります。等級は1~20等級までありますが、最初は6等級からスタートし、事故が無ければ毎年1等級ずつ上がり割引率が高くなります。
保険を使うような事故を起こした場合は、等級が下がり割引率が低くなります。セカンドカー割引は、1台目の自動車保険の等級が11等級以上の場合に、2台目の契約を通常の6等級からスタートするのではなく、1つ上の7等級からスタートさせることができます。
このようにセカンドカー割引を活用すると、子の保険料を安く抑えることができます。2台目の所有者が1台目の所有者と同じでなくても、1台目の記名被保険者・配偶者・同居の親族が所有者であれば適用されます。また、このセカンドカー割引は保険会社が別であっても適用できます。
【ケース4】
同居の子が家族の車を譲り受ける場合
●等級の引き継ぎ
家族間で自動車を譲り渡しするときに、自動車保険の等級も引き継ぎすることができます。例えば、もう運転しなくなってきた同居の祖父の車を孫が譲り受け、祖父の自動車保険を引き継げば、高い等級もそのまま引き継げ、保険料を安くすることができます。
この等級引き継ぎは、記名被保険者の配偶者、同居の親族であれば可能です。親族で引き継ぎができるのは「同居」している人であり、「別居」の場合は適用外になる点には、注意しましょう。等級を引き継ぎたい場合は、同居しているうちに手続きをしておくことがポイントです。

-
コラム執筆者プロフィール
宮一 幸子 (ミヤイチ サチコ) マイアドバイザー.jp®登録 - CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、キャリアコンサルティング技能士2級、DCアドバイザー、住宅ローンアドバイザー。
3歳と0歳の子育てと保険会社勤務をしながらファイナンシャルプランナー取得。
1998年独立。以来ファイナンシャルプランナーとしての仕事を続けてきました。
人とのつながりの上の自分があることを忘れずに出会いを大切に仕事をしていきたいと思っています。

-
コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー 宮一 幸子
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
今すぐ相談したい方はこちら
![]()