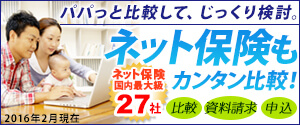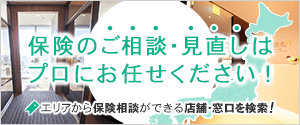判断能力を失ったときの医療保険契約について

判断能力を失うということはどういうことでしょうか。
それは、読んで字のごとく物事を判断できなくなるということです。
高齢期に判断能力が失われる病気として「認知症」があり、厚生労働省の推計によると、認知症の方の数は平成24年には300万人を突破すると見込まれています(平成22年厚生労働省「日常生活自立度Ⅱ(※)以上の人の推計」による)。
判断能力を失うと、日常における様々な「契約」をすることが困難になります。日常生活で最も身近な「契約」は買い物で、モノを買うということは契約書を交わすような堅苦しいものではありませんが、売る側と買う側の契約で成立するものです。
そして、保険の加入も「契約」に基づくものです。
医療保険契約の場合、契約者本人の判断能力が無くなったときには、どのようなことが起こるのでしょうか。
まず、お金の管理が難しくなり、保険料の支払いが滞ってしまうということが起こるでしょう。また、保険を契約していることを忘れてしまうため、医療保険の存在が分からなくなったり、保険証書が見つかったとしても、必要なときに本人が給付金請求をすることが難しくなったりします。
では、あらかじめどのような対策をすれば良いのでしょうか。
まずは、本人にまだ判断能力があるうちにできることを列挙します。
支払いに関しての滞納を防ぐには、口座振替にしている場合、年金等の収入のある口座に変更しておきましょう。まとまったお金がある場合は、保険料を前納してしまう等の方法もあります。
そして保険契約の存在を家族に知らせておき、保険証書等の大事な書類の保管場所も家族に知らせておきましょう。
また、本人による給付金請求ができなくなることに備えて、家族が代わりに請求できる「指定代理請求特約」を付けておきましょう。
これらは、本人が判断能力のあるうちにできることです。
次は、本人の判断能力が無くなってしまったあとの対策です。
この場合は、家族のフォローが必要です。
そもそも保険の契約をしているかどうかが分からない場合、どのように調べれば良いのでしょうか。
まずは、保険会社への支払いの形跡があるかを調べてみましょう。預金通帳がある場合は、口座振替の形跡があるかどうか、または、保険会社からの領収書等が残っていないかというところから探っていきます。同時に、保険証書も探してみると良いですね。
保険会社名さえ分かれば、照会ができます。
給付金の請求については「指定代理請求特約」の付いている保険であれば、家族が請求することができます。
この特約が付いていない場合は、まず、保険会社に相談してみましょう。
本人の状態や字が書けるか書けないか等も伝えることが必要です。保険会社によって判断が違うため、まずは相談してみてください。
通常、本人の判断能力が無くなった場合、「成年後見人」を付けて、本人の代わりに法律行為をしてもらうことになります。
成年後見人は誰でもなることができるので、家族がいる場合は、家族の方がなるのが良いでしょう。
このように、判断能力が無くなると、医療保険契約をしていても活用できない事態になりかねません。元気なうちの対策が肝要です。
※日常生活自立度Ⅱとは、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる状態のことです。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
今すぐ相談したい方はこちら
![]()