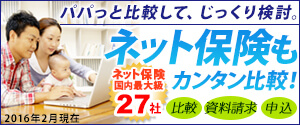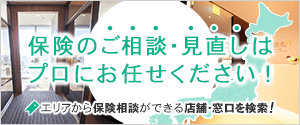医療保険の入院給付

民間の医療保険は、入院1日につき5,000円や10,000円といった一定金額が支払われるという入院給付が中心で、1入院あたりの支払限度日数と通算支払限度日数が設けられています。
入院日数については、厚生労働省が毎年「患者調査」というものを行っていて、そのなかで退院患者の平均在院日数を調査・公表しています。これをみると近年、平均の入院日数は、全国的にどんどん短くなっています。その背景には、医療技術の進歩とともに、医療費抑制のための政策があると考えられます。
病院の収入は、保険診療の場合、診療報酬として点数制によって定められていますが、入院に対する点数(入院基本料)は、平均在院日数や個別の入院日数が一定の日数以内であれば、1日当たりの点数(すなわち、料金)が多くもらえるように設定されています。また、大病院を中心に導入された「DPC/PDPS(診断群分類別1日当たり包括支払制度)」という新たな方式では、入院期間が長くなるほど1日当たりの診療報酬が少なくなっていく仕組みになっています。
つまり、悪い言い方をすれば、病院にとっては長期入院をなるべく減らして、次々に新しい患者を入院させた方が経営効率がよいということになります。入院日数が短くなっているといっても、必ずしも傷病が完治した場合ばかりではなく、在宅医療や通院治療に移行しているケースも少なくないと思われます。
平均在院日数は、傷病・性別・年齢によって異なりますが、全体で32.8日(平成23年、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏および福島県を除いた数値)となっています。がんについても、通院による投薬治療が中心ということもあって、入院日数は最も長い胃がんの場合で22.6日です。
民間医療保険の入院給付は、入院期間の短期化の傾向を受け、最近は1入院当たりの支払限度日数が60日で、入院1日目から給付が出る・・・といったタイプが主流のようです。支払限度日数が長いほど保険料は高くなる傾向がありますが、では、医療保険はこうした短期入院に主眼を置いたタイプを選ぶほうが合理的なのでしょうか?
そもそも保険とは、貯蓄で賄えない事態に備えることが本来の目的であるはずです。短期間の入院費用なら、貯蓄で賄うことも可能でしょうし、健康保険には高額療養費制度というものがあって、保険診療については、1ヵ月の自己負担額に上限があります(なお、事前に限度額適用認定を申請しておけば、後で還付を受けるまでもなく、初めから支払いを上限額までに止めることができます)。また、入院給付には、医療費支出の補填のほか、働けなくなった場合の収入補償という側面もありますが、(被)雇用者であればまず有給休暇が使え、それを使い切れば、健康保険から傷病手当金として最長1年6ヵ月間、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
平均の入院日数が短期化しているといっても、傷病の種類によっては入院が長期におよぶ例も存在します。前述の点から考えると、むしろ長期入院にこそ保険が必要だと言えるのではないでしょうか。
また、先に述べたように、入院日数が短くなっているということは、その分在宅医療や通院治療にシフトしているということでもあります。病気で働けない場合というのは、何も入院している場合に限ったことではありません。病気やケガの保障を、入院給付主体で備えるという考え方は、そろそろあらためる時期に来ているのかもしれません。

-
コラム執筆者プロフィール
鈴木 克昌 (スズキ カツマサ) マイアドバイザー.jp®登録 - (株)FPスピリット代表取締役、CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、宅地建物取引主任者、1種証券外務員、日本福祉大学福祉経営学部非常勤講師。
早稲田大学法学部卒。
主にシニア世代や単身者の方々を中心に、資産の運用・管理からエンディング・相続手続きまで、ライフプランの実現を総合的にサポートしています。
ファイナンシャルプランナー 鈴木 克昌
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
今すぐ相談したい方はこちら
![]()