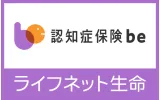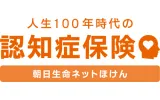アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。
介護・認知症保険
人気ランキング
- 介護保険
- 認知症保険
保険市場 資料請求件数調べ 2025年2月01日~2025年2月28日
ランキングをもっと見る保険市場 資料請求件数調べ 2025年2月01日~2025年2月28日
ランキングをもっと見るその他の保険ランキング
介護・認知症保険の基礎知識
介護保険・認知症保険とは
介護保険とは、介護が必要と認定された場合の支出に備えるための保険です。
介護保険には民間の保険会社が提供する介護保険(以下「民間介護保険」)と公的介護保険があります。民間介護保険は公的介護保険ではカバーしきれない部分を補完することを目的としており、主に、介護サービスにかかる自己負担や、介護状態になった際の経済的な負担に備えることができます。
また認知症保険は、認知症と診断された場合に保険金を受け取ることができる保険です。
各保険会社の介護保険、認知症保険それぞれの内容を確認・比較し、何を重視したいかだけでなく、無理なく保険料を支払い続けられるかどうかも考えながら検討することをおすすめします。
介護保険選びで後悔しないために!知っておくべきポイントと注意点
介護保険の基礎知識
介護保険は、高齢化社会において、介護が必要になった際に経済的な負担を軽減するための保険です。先述のとおり、介護保険には公的介護保険と民間の保険会社が提供する介護保険の2種類があり、それぞれ役割が異なります。
- ①公的介護保険
- 40歳以上の方が加入し、所定の要介護認定または要支援認定を受けた場合に介護サービスを受けられる制度です。市区町村が運営しており、介護サービスの基盤となっています。要介護(要支援)度に応じて受けられるサービスの種類、支給限度額などが異なります。要介護度は、要支援1~2、要介護1~5の7段階に区分されており、要介護度が高くなるほど、より手厚いサービスを受けることができます。
- ②民間介護保険
- 民間の保険会社が提供する保険で、公的介護保険ではカバーしきれない部分を補う役割を担います。例えば、公的介護保険では対象とならない軽度の要介護状態や、介護施設の入居費用などをカバーできます。保険料は、年齢、性別、保険金額、保険期間などによって異なります。保険料の払い方には、月払い、年払いなどがあり、保険商品によって異なります。
| 公的介護保険 | 民間介護保険 | ||
|---|---|---|---|
| 対象者 | 第1号被保険者 (65歳以上の人) |
第2号被保険者 (40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者) |
被保険者 |
| 受給要件 | ・要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態) ・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態) |
要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定 | 介護が必要な所定の状態になった場合 |
| 保険料 | 基準額をもとに、世帯の所得などに応じて決定(市区町村ごとに異なる) | 加入している国民健康保険や職場の健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決定 | 年齢、性別、保険金額、保険期間などによって異なる |
| 保険料支払方法 | 市町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き) ※65歳になった月から徴収開始 |
公的医療保険料と一体的に徴収(健康保険加入者は、原則、事業主が1/2を負担) ※40歳になった月から徴収開始 |
月払い、年払い、などがあり、口座振替やクレジットカードで支払う |
民間介護保険のメリット
民間介護保険は、公的介護保険ではカバーしきれない部分を補う役割を果たします。例えば、介護施設の入居費用や、より手厚い介護サービスを希望する場合など、経済的な負担を軽減できます。まとまった一時金や年金を受け取ることで、介護費用の心配を軽減し、精神的な安定にもつながります。さらに、保険会社や商品によって保障内容を柔軟に選択できるため、自分や家族の状況に合わせた備えができるのも大きな魅力です。
民間介護保険の選び方
民間介護保険を選ぶ際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
- •自分に必要な保障額の考え方
- 将来必要となる介護費用を試算し、公的介護保険でカバーできる部分と、民間の介護保険で準備する必要がある部分をまとめてみましょう。介護期間、介護サービスの種類、介護施設の費用などを考慮し、具体的な金額が算出できると選びやすくなります。
- •保険期間と保険料払込期間の選び方
- 保険期間は、終身保障、一定期間の保障など、さまざまなタイプがあります。保険料払込期間も、保険期間と同じ期間、一定年齢までなど、さまざまです。自分のライフプランに合った保険期間と保険料払込期間を選択しましょう。
- •特約の選び方
- 認知症保障、特定疾病保障などさまざまな特約があります。既契約の保険の保障内容を確認し、自分の家族構成や健康状態などを考慮して、必要な特約を選びましょう。
- •保険会社の選び方
- 保険会社の信頼性、保険金支払い実績などを確認しましょう。ソルベンシー・マージン比率や格付け情報、過去の支払い実績や顧客満足度などを参考に、複数の保険会社を比較検討することをおすすめします。
民間介護保険に入るべき人とは?
民間介護保険は、年齢的には40~50代以降の方におすすめです。また、公的介護保険の限度額以上のサービスを希望する方や、将来的な介護度の悪化に備えたい方にとっても有効です。
さらに、老後資金が十分でない方や、介護を担う家族に負担をかけたくない方も検討しましょう。特に長期間の介護が予想される認知症などのリスクがある場合は重要です。一人暮らしや高齢夫婦のみの世帯は外部サービス利用の可能性が高く、そのための備えとして役立ちます。
また、持ち家を維持したい方や、将来的に親の介護と仕事の両立に不安がある方にとっても、介護保険は経済的な安心材料となるでしょう。
少しでも将来への不安がある場合は、まず保険のプロに相談し、自分に最適な商品を見つけるところから始めてみましょう。
認知症保険とは?メリットや選び方を徹底解説!
なぜ今、認知症保険が注目されているのか
日本は超高齢社会を迎え、認知症患者数は増加しています。厚生労働省の資料によれば、2025年には65歳以上の認知症患者数が約700万人に達するとされており、65歳以上の約5人に1人が認知症になるとの推計もあります。※1
認知症の経済的負担については、患者本人の医療費・介護費用だけでなく、家族の介護離職による収入減少なども考えておく必要があります。特に、認知症による要介護状態が長期化することで、経済的負担が長期間続いた場合、家計への打撃は計り知れません。
公的保障では、要介護認定や要支援認定による介護保険サービスはありますが、いずれも限定的です。介護保険サービスには利用限度額があり、それを超える部分は全額自己負担となるのが現状です。
このような背景から、認知症に特化した民間介護保険の商品が注目を集めています。これらの保険は、認知症と診断された際の一時金支給や年金形式の給付など、公的保障では補いきれない部分をカバーできるというメリットがあります。
※1 出典:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」(2017年7月改訂版)
認知症保険と介護保険の違い
認知症保険と介護保険は、どちらも将来の介護リスクに備えるものですが、保障内容や特徴に大きな違いがあります。認知症保険は、その名のとおり認知症と診断された場合に保険金が支払われる商品です。一方、介護保険は要介護状態全般に対応するもので、身体的な障害や老衰など、認知症以外の原因による介護状態も保障の対象となります。
認知症保険の最大の特徴は、認知症に特化した保障設計にあります。具体的には、認知症の診断確定時に一時金が支払われるタイプや、認知症と診断された後に継続的に年金形式で給付金が支払われるタイプがあります。最近では、軽度認知障害(MCI)と診断された段階で一部給付を行う商品も登場し、認知症に対して早期対応したいというニーズに応えています。
一方、従来の民間介護保険は、公的介護保険の要介護認定(主に要介護2以上)に連動して給付されるケースが多く、身体的な障害と認知症による介護を区別していません。そのため、認知機能の低下が主な症状で身体機能は比較的保たれている初期の認知症患者の場合、要介護度が低く評価され、十分な給付を受けられないケースがあります。
知っておきたい認知症保険の選び方
認知症保険を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを押さえることで、自分に最適な保険を見つけることができます。
第一に確認すべきは保障内容、特に認知症の定義と給付条件です。保険会社によって認知症の定義は異なり、「器質性認知症」のみを対象とするものから、より広い定義で保障するものまでさまざまです。また、近年注目されているのが軽度認知障害(MCI)の段階から給付対象とする商品です。MCIは認知症の前段階とされ、この段階から適切な治療をおこなうことで、進行抑制にも繋がります。
次に、給付金の受取方法も選択のポイントとなります。認知症保険の給付金には、一時金タイプと年金タイプがあります。一時金タイプは診断確定時に一括で保険金を受け取るもので、初期費用(住環境の整備や介護用品の購入など)に対応しやすい特徴があります。一方、年金タイプは定額の給付金を定期的に受け取るもので、長期にわたる介護費用に対応しやすくなっています。自分のニーズや家族の状況に合わせて、適切な受取方法を選ぶことが重要です。
最後に、付帯サービスも選択ポイントです。認知症保険には、介護に関するサービスや認知症予防のためのサービスなどが付帯されている場合があります。これらのサービスは保険金という金銭的保障に加えて、実際の介護負担を軽減する役割を果たします。商品によって特徴が異なるため、本当に必要な保障と付帯するサービスは何かを見極めることが大切です。
認知症保険は比較的新しい保険商品であり、各社の商品は日々進化しています。最新の情報を収集し、自分自身や家族の状況、経済状況などを総合的に判断して、最適な保険を選ぶことが重要です。また、専門家のアドバイスを受けることも、適切な選択をするための有効な手段といえるでしょう。
- ※このページのランキングは、当社WEBサイト「保険市場」の取扱保険商品において、上記期間の資料請求件数・ネット申込み件数に基づいて当社が作成したものであり、保険商品間の優劣を意味するものではありません。また、期間内に「保険市場」にて取り扱いのあった商品のみの掲載となります。あらかじめご了承ください。
- ※商品の詳細はパンフレットや契約概要等を、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報等を必ずご確認ください。
総合窓口
相談予約専用窓口
自動車保険・火災保険窓口