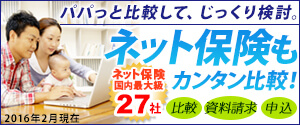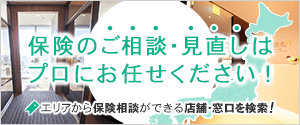火災保険の対象を決める

はじめに
火災保険は建物と家財を分けて契約するため、保険の対象は、「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」の3つに分けられます。
建物のみに保険をかけた場合、火災、落雷等の災害や、漏水による水濡れ等の災害以外の事故による建物部分の損害については補償されますが、テレビや冷蔵庫等の家電、ソファやベッド等の家具に対しての損害については、補償の対象外になります。
ですから一般的には、賃貸住宅にお住まいの方は家財のみを保険の対象にした火災保険へ、持ち家の方は建物と家財の両方をカバーする火災保険への加入を検討することになります。以下、住まいの違いによる保険対象の選び方についてみていきます。
賃貸住宅の場合
賃貸住宅の場合、建物に対する火災保険は家主が契約しています。入居者は、入居者が所有する家財に対して、火災保険を掛けることになります。
また、過失によって借りている部屋に損害を与えた場合に、家主に対して発生する損害賠償責任に備えるには、火災保険に「借家人賠償責任補償特約」を付帯する必要があります。
戸建ての持ち家の場合
住宅ローンを利用する場合、金融機関が債権を保全する目的で、火災保険への加入を求める場合があります。個々の金融機関で住宅ローン利用者専用の火災保険を用意していますが、住宅ローンを利用するからといって、必ずしもその金融機関が用意した火災保険に加入しなければならないということはなく、一般の火災保険への加入も選択できます。
フラット35など、独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受けた場合は、建物については、火災保険(任意の火災保険または法律の規定による火災共済)に必ず加入しなければなりません。フラット35を利用する場合は、住宅ローン完済まで火災保険の契約を継続しないと、金銭消費貸借契約に違反することとなり、ローン残額(融資金の残額)を一括して支払わなければならなくなります。
なお、住宅ローン完済後も、火災等のリスクに備えるためには、建物と家財の両方について火災保険への加入が必要です。
分譲マンションの場合
マンション等の区分所有建物では、各住戸部分は入居者(各区分所有者)の単独所有となる「専有部分」と、エレベーターや階段、エントランスのように、区分所有者全員の共有となる「共用部分」の2つの部分から構成されますので、以下のような2つのケースが起こります。
一般的なケースは、マンション管理組合が火災保険の契約者となり、共用部分の財物全体を補償対象とする火災保険を契約します。この契約方式を、「共用部分一括付保方式」といいます。この方式の火災保険の契約を行っているマンションの入居者は、専有部分のみ補償する「建物と家財」の火災保険への加入を考えることになります。
ただし、マンション管理組合が共用部分の財物全体を補償対象とする火災保険に入ることは、法律等で義務化されている訳ではありませんので、購入検討中のマンションが共用部分一括付保方式の契約をしていないケースも考えられます。
この場合の対処方法として、「個別付保方式(専有部分+共用部分の共有持分)」という契約方式で、共用部分のうち自己の共有持分に対して火災保険を契約する方法があります。
しかし、全ての入居者が同じ補償内容の火災保険を契約しているとは限らず、補償内容にバラつきがあることが考えられます。
マンション購入時には、管理費や修繕積立金以外にも、火災保険等の災害や事故に対する補償部分のチェックも必要になります。
まとめ
以上、賃貸住宅、戸建ての持ち家、分譲マンションの3つのケースについて、「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」のうち、どの保険対象で契約すればいいのかということについてみてきました。
火災や風災等の災害や水濡れ、破損、盗難等の事故に備えるには、火災保険のどのような補償が必要になるのかといった細かい部分につきましては、別の機会に取り上げてまいります。

-
コラム執筆者プロフィール
恩田 雅之 (オンダ マサユキ) マイアドバイザー.jp®登録 - 1959年東京生まれ。
2004年3月にCFP®資格を取得。
同年6月、札幌にて「オンダFP事務所」を開業。
資産運用をテーマとした個人向けのセミナー講師や3級、2級ファイナンシャル・プランニング技能士取得の講師やライフプラン、金融保険関連のコラムやブログの執筆など中心に活動中。
ファイナンシャルプランナー 恩田 雅之
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
今すぐ相談したい方はこちら
![]()